祖父母の呼び方
2016.04.21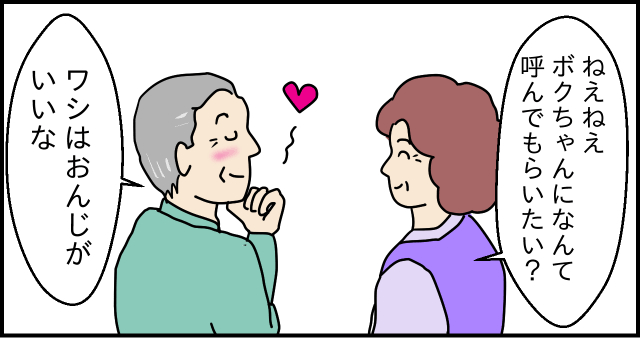 首都圏から拡大、「じいじ・ばあば」 昭和の時代、祖父母の呼び方としては、「おじいさん・おじいちゃん」、「おばあさん・おばあちゃん」が多数派でした。 […]
続きはこちら
首都圏から拡大、「じいじ・ばあば」 昭和の時代、祖父母の呼び方としては、「おじいさん・おじいちゃん」、「おばあさん・おばあちゃん」が多数派でした。 […]
続きはこちら
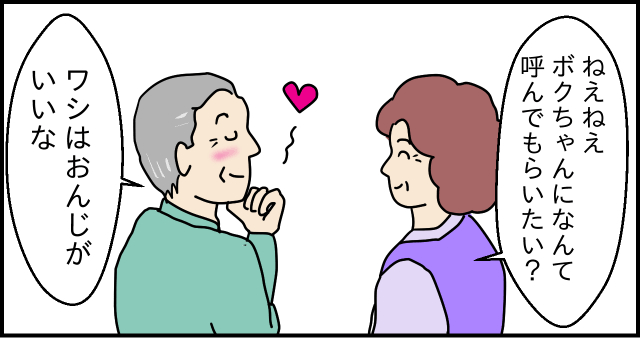 首都圏から拡大、「じいじ・ばあば」 昭和の時代、祖父母の呼び方としては、「おじいさん・おじいちゃん」、「おばあさん・おばあちゃん」が多数派でした。 […]
続きはこちら
首都圏から拡大、「じいじ・ばあば」 昭和の時代、祖父母の呼び方としては、「おじいさん・おじいちゃん」、「おばあさん・おばあちゃん」が多数派でした。 […]
続きはこちら
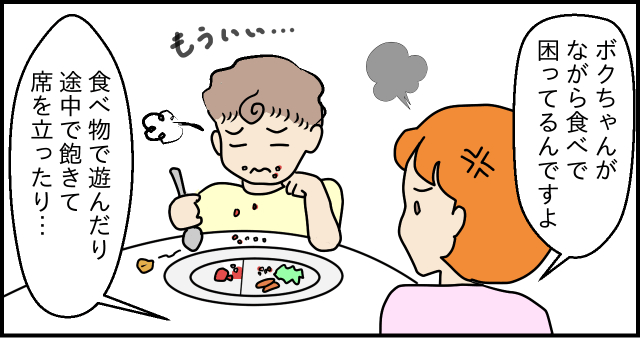 しつけの悩み 近年、近親者による子どもの虐待死事件が相次いで起こっています。「しつけ」と称して、殴る、蹴るなどの暴力行為により子どもを死亡させる事 […]
続きはこちら
しつけの悩み 近年、近親者による子どもの虐待死事件が相次いで起こっています。「しつけ」と称して、殴る、蹴るなどの暴力行為により子どもを死亡させる事 […]
続きはこちら
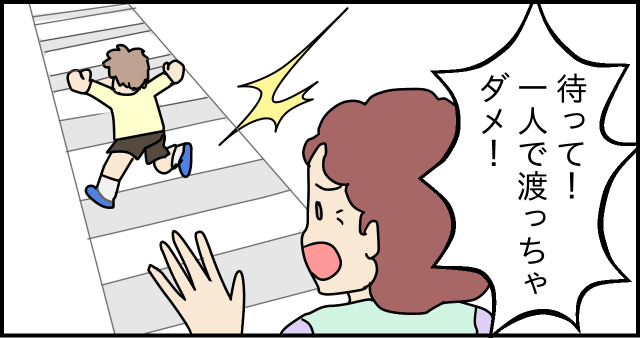 迷子紐とは 子どもがようやく歩けるようになって、一緒に外出するようになると、思った以上にヒヤリ・ハットが多いものです。 しっかり手をつないでいても […]
続きはこちら
迷子紐とは 子どもがようやく歩けるようになって、一緒に外出するようになると、思った以上にヒヤリ・ハットが多いものです。 しっかり手をつないでいても […]
続きはこちら
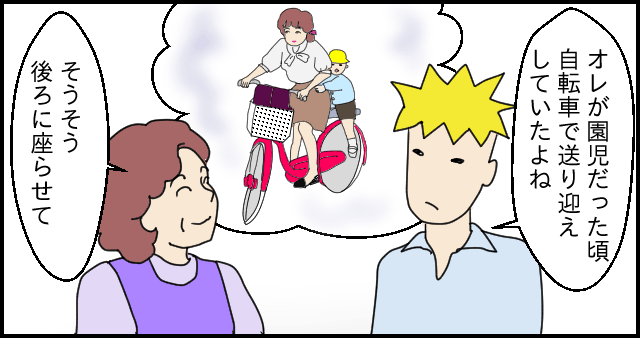 子ども乗せ自転車の出現 幼稚園や保育所の送り迎えで、自転車の前カゴと後ろ座席に子ども2人を乗せて走る通勤姿のパパママ。朝夕おなじみの光景です。 昭 […]
続きはこちら
子ども乗せ自転車の出現 幼稚園や保育所の送り迎えで、自転車の前カゴと後ろ座席に子ども2人を乗せて走る通勤姿のパパママ。朝夕おなじみの光景です。 昭 […]
続きはこちら
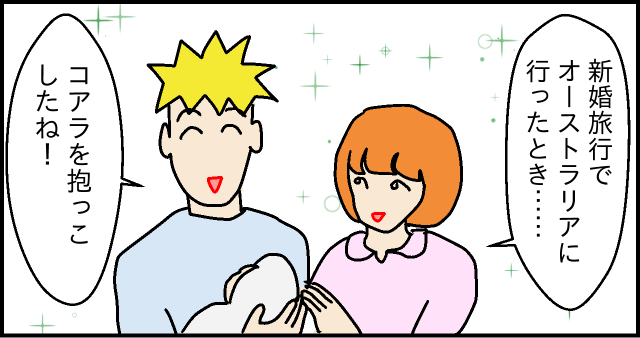 揺さぶられっこ症候群とは 平成以降、赤ちゃんを取り巻く新しい社会問題として、特にマスコミが大きく取り上げたのが、「乳幼児突然死症候群(SIDS)」 […]
続きはこちら
揺さぶられっこ症候群とは 平成以降、赤ちゃんを取り巻く新しい社会問題として、特にマスコミが大きく取り上げたのが、「乳幼児突然死症候群(SIDS)」 […]
続きはこちら
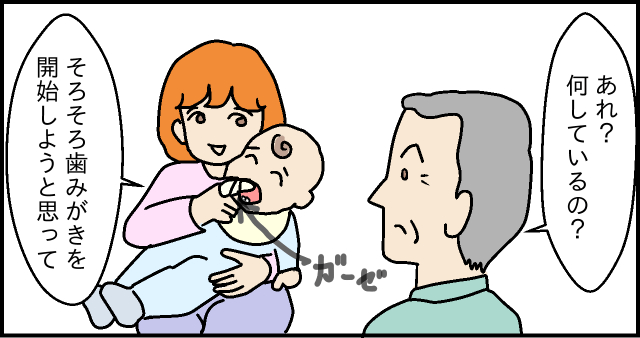 子どもの虫歯が激減! 平成元(1989)年より、日本では「8020(ハチマル・ニイマル)運動」が進められています。これは、「高齢者(80歳)でも2 […]
続きはこちら
子どもの虫歯が激減! 平成元(1989)年より、日本では「8020(ハチマル・ニイマル)運動」が進められています。これは、「高齢者(80歳)でも2 […]
続きはこちら
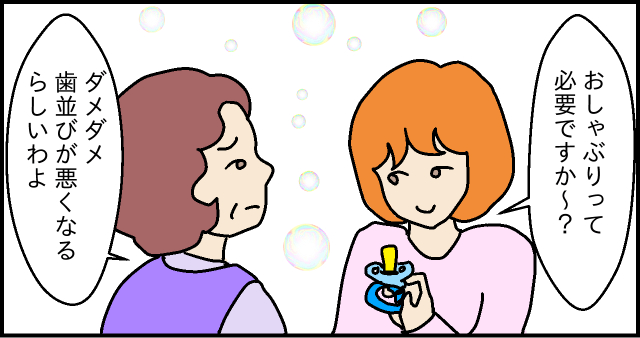 おしゃぶりのメリット、デメリット 欧米のイラストで描かれる赤ちゃんは、必ずゴム製の乳首「おしゃぶり」をくわえています。でも、日本ではおしゃぶり姿の […]
続きはこちら
おしゃぶりのメリット、デメリット 欧米のイラストで描かれる赤ちゃんは、必ずゴム製の乳首「おしゃぶり」をくわえています。でも、日本ではおしゃぶり姿の […]
続きはこちら
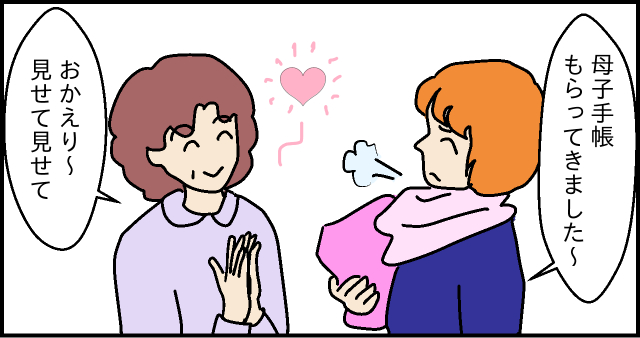 母子健康手帳の歴史 日本では、妊娠していることがわかったら、現在住んでいる市区町村に「妊娠届」を提出する必要があります(義務ではなく勧奨)。このと […]
続きはこちら
母子健康手帳の歴史 日本では、妊娠していることがわかったら、現在住んでいる市区町村に「妊娠届」を提出する必要があります(義務ではなく勧奨)。このと […]
続きはこちら
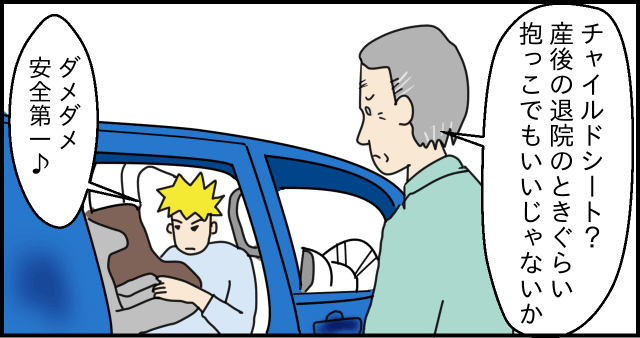 チャイルドシートのはじまり 赤ちゃんを自動車に乗せるとき、現在はチャイルドシートの使用が義務づけられています。では、昔はどうだったのでしょうか。 […]
続きはこちら
チャイルドシートのはじまり 赤ちゃんを自動車に乗せるとき、現在はチャイルドシートの使用が義務づけられています。では、昔はどうだったのでしょうか。 […]
続きはこちら
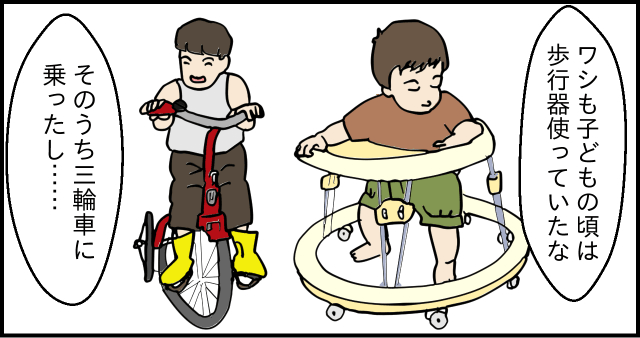 歩行器のはじまり 昔は、つかまり立ちしかできない赤ちゃんの歩く訓練のために、キャスターがついた補助器具である「歩行器」が使われていました。 今でも […]
続きはこちら
歩行器のはじまり 昔は、つかまり立ちしかできない赤ちゃんの歩く訓練のために、キャスターがついた補助器具である「歩行器」が使われていました。 今でも […]
続きはこちら